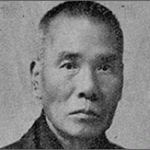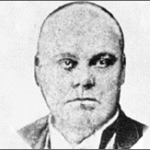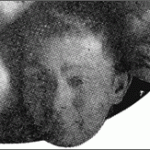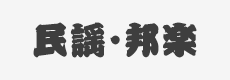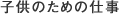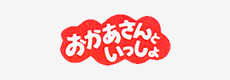京都の五代目橘家圓太郎噺家アーカイブ
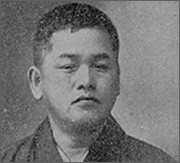
演目解説
独逸ライロフォン 大正初期発売
酒のみの親子が禁酒を誓い合うということは、ありそうな話である。酔っぱらいの噺は、テーマが身近だということもあり、幅広い客層に受けるネタなので、昔から多くの落語家が手がけてきた。酔いっぷりも演者によってそれぞれ違う。しかし、酒飲みの本性は、今も昔も変わらない。圓太郎は得意の音曲を生かし、ふんだんに唄を盛り込んで音曲性豊かな演出をとったところが喜ばれ、よく売れたレコードだった。明治末期のライロフォン・レコードより収録。(岡田則夫)
演者基本情報
| 本名 | 斎藤徳次郎 未詳~昭和14年9月18日 | 改名と師匠 | 三遊亭?小雀(明治16年頃.圓馬2) 三遊亭伯馬(明治20年代初め?) 橘家圓三(明治25年頃.圓生4) 四代目橘家小圓太(明治29年11月) 五代目橘家圓太郎(明治35年2月) |
|---|---|---|---|
| 出身 | 東京 | ||
| 活躍年代 | 明治16年頃~明治末 | ||
| 出囃子 |
演者解説
明治16年頃入門。
明治半ば、神田生れで音曲狂いの若者が四代目圓生門で圓三を名乗って間もなく京都へ駆け落ち決行。小圓太で帰京ののち五代目圓太郎を頂戴し、再び上方へ逆戻り。巧みな話術と美声の音曲師で、上方ですっかり名を上げ寄席(京都新京極の笑福亭)も経営した切れ者。(橘左近)
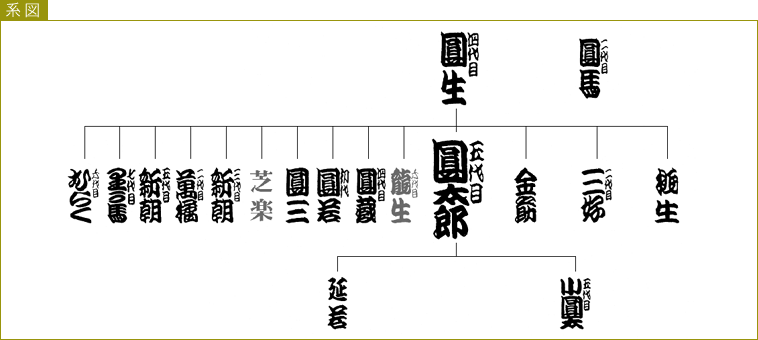
紹介している音源や資料は、「ご存じ古今東西噺家紳士録」「古今東西噺家紳士録」でお楽しみいただけます。