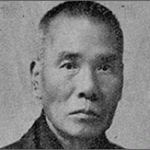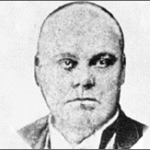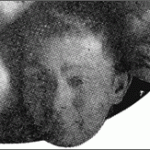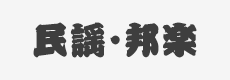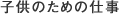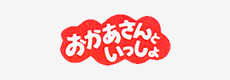三代目 三遊亭金馬名演集名演集

抱腹絶倒の明快落語
わかりやすくて楽しい落語が金馬の持ち味。ニッポン放送、東宝名人会、文化放送に残る落語の中からセレクトした金馬十八番集。
| 収録内容 | ||
| タイトル | 演目 | あらすじ |
|---|---|---|
| 三代目 三遊亭金馬名演集(一) (PCCG00782) |
居酒屋 昭和三十五年一月収録 ニッポン放送 | 居酒屋の小僧に無理難題を言ってからみだす酔っ払い。それを小僧がかわすので、酔っ払いは更に難題を吹っかけていく。 |
| 目黒のさんま 昭和三十三年九月十四日放送 文化放送 | 馬を駆って遠乗りに出かけたお殿様。空腹に堪え兼ねて、農家から焼きたてのサンマをわけてもらう。屋敷に戻ってもその味が忘れられないお殿様は・・・。 | |
| 長屋の花見 昭和三十九年四月一日放送 文化放送 | 花見に出かけるも、酒が番茶で、肴が大根と沢庵では盛り上がるわけが無い。貧乏長屋の住民達による貧乏花見の様子とは? | |
| 唐茄子屋政談 収録年月日不詳 ニッポン放送 | 商家の若旦那の徳三郎が、吉原遊びが過ぎて勘当になる。親のありがたさがわかったときにはもう遅い。吾妻橋から身を投げようとして、通りかかった伯父さんに助けられる。 | |
| 三代目 三遊亭金馬名演集(二) (PCCG00783) |
孝行糖 昭和三十六年十一月収録 ニッポン放送 | 親孝行ぶりにより、お上からご褒美を頂戴した与太郎。周囲の人間は、折角いただいたご褒美を無駄にしてはいけないと、与太郎に商売を始めさせる。 |
| 片棒 昭和三十九年四月一日放送 文化放送 | 主人公は赤螺屋という倹約家の主人。年を取り、そろそろ先も見えてきたので、一代で築いた身代を三人息子の誰に譲るかで悩んでいる。そこで考えたのは・・・。 | |
| 三軒長屋(上・下) 昭和三十三年八月十、十七日放送 文化放送 | 舞台は明治中頃の三軒長屋。横町の手前から、鳶頭の政五郎、伊勢勘のお妾さん、端に剣術の先生が住んでいる。両隣がうるさいとお妾さんが伊勢勘の旦那に泣きつくと・・・。 | |
| 三代目 三遊亭金馬名演集(三) (PCCG00784) |
金明竹 昭和三十七年五月収録 ニッポン放送 | 与太郎が店番をしているところに中橋の加賀屋佐吉から使いのものがやってくる。上方弁の早口で口上を述べるが与太郎にはさっぱりわからない。 |
| 薮入り 昭和三十八年七月十二日放送 文化放送 | 商家に奉公に出ていた小僧が休暇をもらい、実家へ帰る。帰ってきた我が子の成長ぶりに父親は驚き喜んでいると、母親が息子の財布の中から大金を見つける・・・。 | |
| くしゃみ講釈 昭和三十九年四月一日放送 文化放送 | 講釈を聞いている内にいびきをかいてしまったある男。無愛想な対応をとった講釈師が気に食わないので、困らせてやろうと計画を立てる。 | |
| 三代目 三遊亭金馬名演集(四) (PCCG00785) |
万病圓 昭和三十六年二月収録 ニッポン放送 | 侍が銭湯・菓子屋・古着屋・紙屋をひやかしてまわる。最後に訪れた店で、万病円という薬を見つけ、また、難癖をつける。 |
| 寄合酒 昭和三十三年九月二十一日放送 文化放送 | 若い男が集まり、酒を飲もうとなるのだが、あいにく持ち合わせがない。そこでみんなで顔のきく店などを回って、酒と肴を集めようとする。 | |
| 三人旅(上・下) 昭和三十三年六月十五、二十二日放送 文化放送 | 『三人旅』という噺から『鶴屋善兵衛』の件。小田原の近くまでやって来た三人。一人が足にマメをこしらえたものだから、馬子に勧められて馬に乗るのだが・・・。 | |
| 三代目 三遊亭金馬名演集(五) (PCCG00786) |
一目上り 昭和三十三年一月一日放送 文化放送 | 八っつぁんがご隠居の家を訪ね、掛け軸のほめ方を教わる。何かをほめるということは難しいもので、八っつぁんは付け焼刃で教わったことを他所で試して失敗をする。 |
| 蔵前駕籠 昭和三十八年十月十六日収録 ニッポン放送 | 蔵前国技館があったあたりの、蔵前通りが舞台。明治維新前の、不安におののく江戸の世相が背景。追い剥ぎを恐れる駕籠屋の前に客が現れ、吉原まで駕籠を頼むのだが・・・。 | |
| 夢金 昭和三十七年十二月収録 ニッポン放送 | 船頭の熊蔵が侍と若い娘をのせて船で雪の隅田川を下る。途中、侍がとんでもない話を熊蔵に持ちかける。大金を持っている娘を殺し、二人で金を山分けしようというのである。 | |
| 三代目 三遊亭金馬名演集(六) (PCCG00787) |
たらちね 昭和三十三年二月二十三日放送 文化放送 | 長屋に住む八五郎に大家さんが縁談を持ってきた。お嫁に来た女性は働き者で器量もいいのだが、言葉が丁寧すぎる欠点があって・・・。 |
| 蛙茶番 昭和三十九年五月三十一日収録 東宝名人会 | 町内の連中が集まって素人茶番を演る。狂言は『天竺徳兵衛』ときまる。いろいろな役もめなどあって、舞台番に八公がえらばれる。 | |
| 錦の袈裟 昭和三十九年五月三十一日収録 東宝名人会 | 町内の若い連中が、となり町の連中に負けないようにと、趣向をこらして吉原へ集団登楼しようということになる。錦のふんどしを締めていこうと相談がまとまるが・・・。 | |
| 三代目 三遊亭金馬名演集(七) (PCCG00788) |
やかん 収録年月日不詳 ニッポン放送 | 物識りを自認する旦那のところへ、八五郎がやって来ていろいろときく。他愛ないやりとりのあと、「やかんはなぜ“やかん“という」かと八五郎がたずねると・・・。 |
| 堪忍袋 昭和三十三年二月収録 ニッポン放送 | 夫婦喧嘩の仲裁に入るある旦那。おかみさんに、小さな袋をひとつ縫い上げて「堪忍袋」とし、愚痴や不満があれば、その袋にしゃべり込むようにと知恵を授けるが・・・。 | |
| 山崎屋 収録年月日不詳 文化放送 | 吉原の遊女を妻に迎えようとする山崎屋の若旦那。父親が許さないことは百も承知なので、武家屋敷に奉公に出ていた女性ということにする。 | |
| 三代目 三遊亭金馬名演集(八) (PCCG00789) |
小言念仏 昭和三十九年四月一日放送 文化放送 | 朝起きて念仏を唱えることが日課の男。ところが周辺で起こることが気になって、小言を口にしながら、念仏を続ける始末・・・。 |
| 転宅 昭和三十六年九月六日収録 ニッポン放送 | お妾さんのところに泥棒が入る。度胸のいいお妾さんは泥棒と夫婦約束をし、明くる日、また迎えに来てくれと追い返す。 | |
| 池田大助(上・下) 昭和三十三年一月五、十二日放送 文化放送 | 大岡越前守が市中で、奉行ごっこの奉行役をしている子どもに目を留め、町役人同道の上、奉行所に出頭するよう申し付ける。 | |
| 三代目 三遊亭金馬名演集(九) (PCCG00790) |
お化け長屋 収録年月日不詳 ニッポン放送 | 長屋の中の一軒が空き家になっている。そこを物置代わりとして使っている長屋の連中は、よその人に借りられては困ると怪談話をでっちあげる。 |
| 二人癖 昭和三十三年六月八日放送 文化放送 | 何かというと「つまらねえ」という男と、何かというと「うめえ」という男がお互いの口癖を責め、これから先、口癖を言ったら罰金を払うことを決める。 | |
| 妾馬 昭和三十二年十二月一日放送 文化放送 | 身分差のきびしかった封建時代。職人の八五郎が大名と直に、それも友だちのような口をきき、酒をのむ。八五郎は言うことなすことトンチンカンで・・・。 | |
| 三代目 三遊亭金馬名演集(十) (PCCG00791) |
弥次郎 昭和三十三年三月十六日放送 文化放送 | 隠居のもとに現れた弥次郎は、まるで講釈を語るように、次々に嘘をついていく。その嘘の中味とは? 講釈出身の金馬に合った十八番の一席。。 |
| 二十四孝 昭和三十七年二月収録 ニッポン放送 | 乱暴な男が、おっかさんへ離縁状を書いてくれと家主のところへ来る。家主は唐土に伝わる二十四孝の話をし、親孝行をすすめる。男は早速家に帰って実行しようとするが・・・。 | |
| 茶の湯 収録年月日不詳 ニッポン放送 | 蔵前の大店の主人が隠居して、小僧の定吉一人を連れて根岸に住む。退屈なので茶の湯をはじめようと思うが、まるっきり作法も知らない。 | |
| 三代目 三遊亭金馬名演集(十一) (PCCG00792) |
権兵衛狸 昭和三十九年四月一日放送 文化放送 | 権兵衛は田舎の一軒家でひとり暮らし。毎晩、戸を叩いて名前を呼ぶものがあるが、戸をあけると誰もいない。ある晩、戸をあけると、一匹の狸が飛び込んで来た。 |
| 真田小僧(上・下) 昭和三十三年六月二十九、七月六日放送 文化放送 | こましゃくれた性格の金坊。父親の気にかかるような話をはじめ、父親が続きを聞きたがると、いい場面にさしかかったところで、話を止めて小遣いをせびる。 | |
| 寝床 昭和三十六年十月十一日放送 ニッポン放送 | 大の義太夫好きの大店の旦那。今夜もみんなに語って聞かせようと、長屋の連中を呼びにやるが、それぞれ理由を付けて拒否反応を示す。 | |
| 三代目 三遊亭金馬名演集(十二) (PCCG00793) |
高尾 収録年月日不詳 ニッポン放送 | 吉原で高尾太夫という花魁が代々いたが、これは仙台公に寵愛を受け、俗に“伊達高尾“で知られた、二代目の高尾太夫の話。 |
| 近江八景 昭和三十二年十一月十日放送 文化放送 | 遊女との仲を易者に占ってもらう男。「女は来るが、腰かけとしてである」と聞いて、男はがっかり。しかし、女が惚れている証拠だと遊女からの手紙を取りだすが・・・。 | |
| 夏どろ 昭和三十三年三月二十六日放送 文化放送 | ある夏の夜、泥棒が長屋に忍び込んだが、そこは貧乏長屋で盗るものは何もない。揚句の果てには、寝ていた男が泥棒にお金をせびってくる始末。 | |
| たがや 昭和三十三年七月二十九日放送 文化放送 | 両国の川開きの当夜。両国橋の上に、一人のたが屋(桶のたがを直す職人)が通りかかる。押されたはずみでたがの輪が外れて、馬で来た武士の笠をはねとばす。 | |
| 三代目 三遊亭金馬名演集(十三) (PCCG00794) |
てれすこ 昭和三十三年二月十六日放送 文化放送 | 奉行が正体不明の魚の名を知っている者を探す。ある男がその魚の名は「てれすこ」と教える。その魚を干物にして、今一度名を尋ねると、今度は「すてれんきょう」と言う・・・。 |
| 七の字 収録年月日不詳 文化放送 | 長屋の下働きをしていた字の書けない七兵衛は、伯父の遺産をもらって出世する。それを聞いておもしろくない長屋の連中は・・・。 | |
| 雑俳 昭和三十三年五月十一日放送 文化放送 | 隠居と八五郎の前に客人が現れ、俳諧の会で秀句に与えられる「天」の評価がもらえるレベルの句はどれかと、句を披露する。 | |
| 艶笑小噺総まくり 昭和三十九年五月三十一日収録 東宝名人会 | 艶笑小噺がメドレーで十数篇入っている。お座敷ならともかく、演芸場で演じられたものとしては、おそらく金馬一世一代の珍品であろう。 | |
| 三代目 三遊亭金馬名演集(十四) (PCCG00795) |
浮世床 昭和三十三年九月七日放送 文化放送 | チョンマゲ時代の髪結床は、町内の連中の社交場であった。自分の番を待つ間、本を読む奴、そのへんで寝ている奴もいるといった具合。男たちが将棋をさしはじめると・・・。 |
| 高野違い 昭和三十三年三月二日放送 文化放送 | 隠居のところで身につけてきたにわか学問を他で披露するのだが、“高野(こうや)“を“たかの“と読んだり、“紫式部“を“鳶色式部“という始末。 | |
| 付き馬 収録年月日不詳 ニッポン放送 | 金がないのに妓夫太郎をだまして登楼した客は、翌朝、妓夫太郎を“付き馬“にして、吉原から浅草まで、たくみな口先きでごまかしながら連れ回していく。 | |
| 随談 変人さま列伝 収録年月日不詳 東宝名人会 | 変人さま“というのは、落語仲間の符丁で“変りもの““奇人“のこと。この種の話は金馬の独壇場で、演芸史上貴重な証言といえる。 | |
| 三代目 三遊亭金馬名演集(十五) (PCCG00796) |
初夢 収録年月日不詳 ニッポン放送 | 正月にふさわしく『初夢』と題しているが、「一富士、二鷹、三茄子」の説明など、いうなれば“漫談““随談“といった、金馬雑学集ともいえる一席。 |
| 浮世根問 昭和三十三年八月三十一日放送 文化放送 | ご隠居が八っつぁんから、物の言われや起こりを問われるので、次々に答えていくという“根問物(ねどいもの)“の一つ。 | |
| 随談 艶笑見聞録 昭和三十九年五月三十一日収録 東宝名人会 | 金馬の年輪と話芸を感じさす随談。体験談を中心に語られるので、聞く客にとって、単なる“のぞき趣味“だけではない楽しさがある。 | |
| 随談 猫の災難 昭和三十八年七月三十一日収録 | 『猫の災難』という落語があるが、それとは異なり、“座談“風な展開で、いろいろ“猫“に因んだ思い出話を語る。「東宝名人会」で、“怪談特集“を演ったときのもの。 | |
ご購入に関するお問い合わせ:(株)ポニーキャニオン
音楽マーケティング部 03-5521-8031
商品内容に関するお問い合わせ:(株)エーピーピーカンパニー 047-302-4070