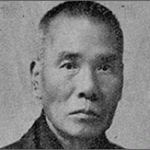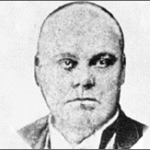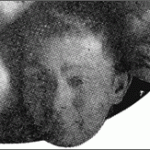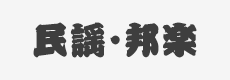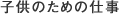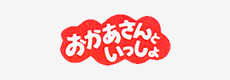二代目蜃気楼龍玉噺家アーカイブ
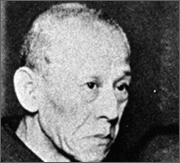
演目解説
パーロフォン 昭和4年発売
この噺は師走の寄席でよく聴くことができる。昔、正月には万歳が門付けをして祝い事をしていたが、いまは萬歳を登場させないで『掛け取り』の題で演じられる。軽妙な尾張萬歳の調子は古風で趣きがある。昔は落語家の層も厚く龍玉のような老練な芸人が大勢いて落語界を支えていたのである。龍玉が残した唯一枚の貴重なレコードである。(岡田則夫)
演者基本情報
| 本名 | 住田金作 文政10年(逆算)~明治22年9月18日 | 改名と師匠 | 立川金作(弘化初年?.金馬2) 初代蜃気楼龍玉(嘉永初年?) |
|---|---|---|---|
| 出身 | 未詳 | ||
| 活躍年代 | 弘化初年~明治22年? | ||
| 出囃子 |
演者解説
弘化初年?入門。
無骨な語り口で『義士伝』『水滸伝』『八百屋お七』など人情噺を得意とし、明治10年代には力を発揮したが、酒と博打で身を持ち崩し辻講釈に落ちぶれ、落胆のうちに没した。(志村)
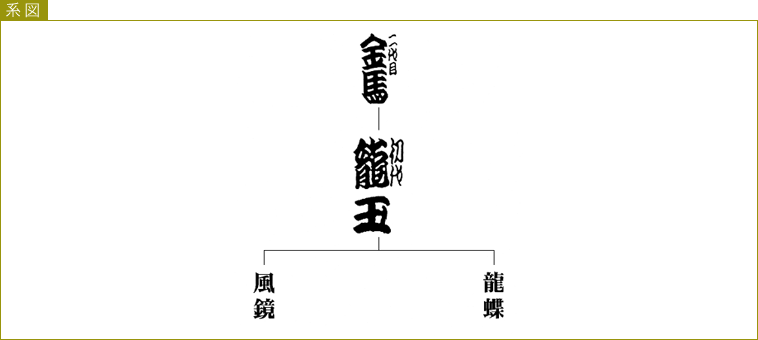
紹介している音源や資料は、「ご存じ古今東西噺家紳士録」「古今東西噺家紳士録」でお楽しみいただけます。