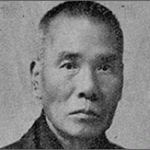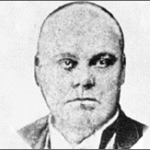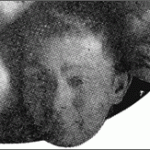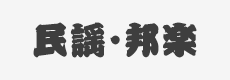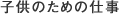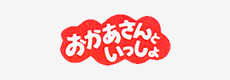ステテコの、鼻の、初代三遊亭圓遊噺家アーカイブ
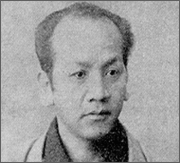
演目解説
英国グラモフォン 明治36年発売
芝居に凝った商家の息子。商用から帰るなり、何から何まで『菅原伝授手習鑑』の寺子屋紛いの真似ばかりをする。目に余った親父が呆れ返って小言を言うと、息子は親父をズンデンドウと取って投げる。「女房喜べ、倅が親父に勝ったわやい」というのがサゲ。これは寺子屋の「女房喜べ、倅がお役に立ったわやい」をもじったものであるが、芝居の寺子屋の科白を知っていないとこのサゲの意味が判らない。前作では圓遊の十八番といわれた『野ざらし』を収録した。(都家歌六)
演者基本情報
| 本名 | 竹内金太郎 嘉永3年5月28日~明治40年11月26日 | 改名と師匠 | しう雀(慶応4年頃.玉輔2) 三遊亭圓遊(明治5年頃?.圓朝1) |
|---|---|---|---|
| 出身 | 東京 | ||
| 活躍年代 | 慶応4年頃~明治40年 | ||
| 出囃子 |
演者解説
慶応4年頃入門、明治13年4月真打。
ステテコで一世を風靡したこの初代圓遊は実際は三代目である。元来圓遊の名は初代金原亭馬生の前名で、二代目は圓朝の門人新朝が継いだのだが、実際にはこの圓遊が名を大きくしたために、いつとはなく初代となってしまったのである。
さてこの圓遊、明治13年浅草の並木亭で一席伺った後、いきなり高座で立ち上がり、じんじん端折りに半股引、「そんなこっちゃなかなか真打にゃなれない、あんよを叩いてせっせとおやりよ」と奇妙な手つき足踏みで踊りだした。この世にも不思議な踊りを見せられて、お客はしばし呆然としてしまった。しかし、やがてそれは驚嘆のざわめきとなり、しまいには小屋も割れんばかりの大喝采になったという。これが圓遊生涯の売り物となったステテコ誕生の一瞬である。そしてそれ以来、彼は落語の後で必ずこのステテコを踊るようになった。トレード・マークのあの大きな鼻をチョいとつまんで捨てる真似をして、尚一層の喝采を博したのである。その最盛期には、一晩でなんと36軒もの掛け持ちをしたという。辞世の句は「散りぎわも 賑やかであれ 江戸の花(鼻)」。(都家歌六)
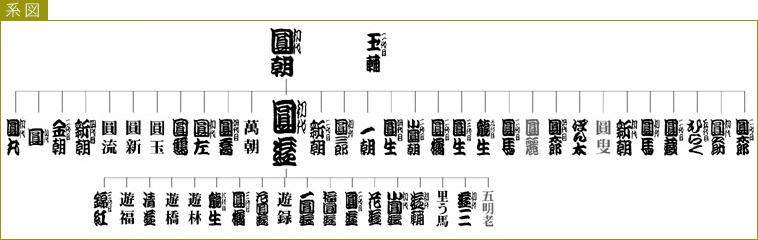
紹介している音源や資料は、「ご存じ古今東西噺家紳士録」「古今東西噺家紳士録」でお楽しみいただけます。