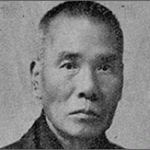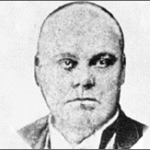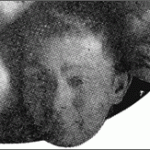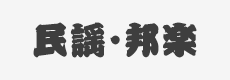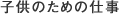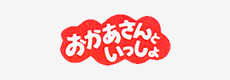おっとせいの四代目柳亭左楽噺家アーカイブ
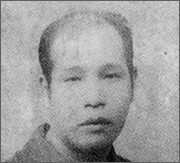
演目解説
独逸ベカ 明治39年頃発売
四代目左楽の音声は明治39年の独逸ベカに『地口』『昔噺柿と栗』『昔噺えび床』の三席がすべてであり、この『地口』は私の恩人である作家正岡容の遺品の中にあったもので、それ以外のものはまだ一度もお目にかかっていない。この録音では、最後喋っているうちに時間が来て、技師に「エッ」と聞き返したまま尻切れトンボで終わっているのが面白い。レコードで聞く限りでも、対話の人物の使い分けがはっきりせず、決して噺のうまかった人とは思えないが、独特のおかしみはあったようで、人間的には人情家で話のよくわかるきわめて善人であったようだ。(都家歌六)
演者基本情報
| 本名 | 福田太郎吉 安政3年1月2日~明治44年11月5日 | 改名と師匠 | 柳亭燕多(明治7年.燕枝1) 柳亭路喬(明治10~11年頃.柳枝3) 初代柳家枝太郎(明治16年頃?) 四代目柳亭左楽(明治26年12月) |
|---|---|---|---|
| 出身 | 東京 | ||
| 活躍年代 | 明治7年~明治44年 | ||
| 出囃子 |
演者解説
明治7年入門、明治17年真打。
その風貌から綽名を”オットセイの左楽”。明治37年から40年まで柳派の頭取を務めた。噺の数の非常に少なかった人で、ある左楽のトリ席で楽屋の連中が彼の持ちネタを面白半分に皆でそっくり出してしまった。そのうちに左楽が現れ、楽屋帳を暫くの間じっと眺めていたが、そのうちスックと立ち上がるや「今日は私のやる噺がありゃァせんナ。では皆さんさようなら」とサッサと帰ってしまったという。非常にケチな人で、いつも千秋楽の割(噺家の給金)を出さなかった。それで彼とは別の人が楽割を出さなかった時に、「左楽でないにワリ呉れぬとは」(からくれないに水くぐるとは)という落首が張り出されたという。(都家歌六)
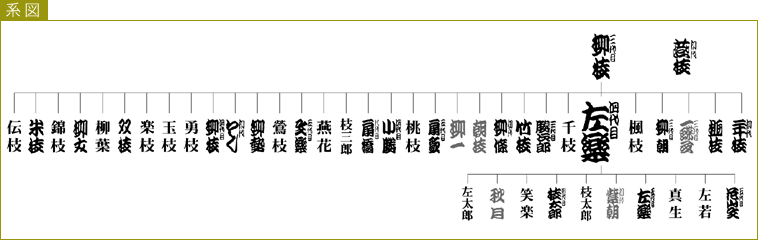
紹介している音源や資料は、「ご存じ古今東西噺家紳士録」「古今東西噺家紳士録」でお楽しみいただけます。